入学式が済んでから、早いもので約2週間が経過しました。
ようやく慣れたと思った頃に、今度はゴールデンウィークという楽しい連休が待っています。
先日、LINEニュースの朝日学生新聞社にこんな記事が掲載されていました。
「五月病の子にかける言葉は?」
実は、わが子にも五月病の予兆?ともいえる症状が出たので、気になっておりました。
連休明けの「五月病」に注意
「五月病」とは、
新人社員や大学の新入生や社会人などに見られる、新しい環境に適応できないことに起因する精神的な症状の総称
引用元:Wikipedia
とあるように、新しい環境や周りの変化についていけないことが原因で起こる症状です。
今や現代病ともいわれる「五月病」にもっとも気を付けたほうがいいのは、ゴールデンウィーク明け。
5月はゴールデンウィークがあり、4月からの緊張感が一気に解き放たれる時期。
その連休が終わると、再び新しい環境に戻ることになります。
しかし五月病になると、再び以前の新しい環境に戻っても、やる気が出なかったり、会社や学校に行くのが億劫だと感じるようになります。
このゴールデンウィークあたりの連休をきっかけとして、五月病となる方が多いようです。
最近では、5月病が6月頃まで長引いて、「6月病」という言葉もあるんだとか。
現代では五月病は低年齢化が進んでいて、大人だけでなくこどもでもかかる場合が増えているそうです。
わが家も五月病の予兆が…
うちの子は小学校に入学して半月、学校生活は今のところ楽しい様子です。
ですが昨日、夕ご飯の時間に初めて「おなかがいたい・・・」と言い出しました。
ご飯もまだ少ししか食べておらず、おなかは空いているはずなのにおなかが痛いというので、これは精神的なものかなと感じました。
学校の様子は毎日さりげなく聞いていますが、特に問題はない様子。
しばらくすると、「おなかいたくなくなった!」と言ってまたご飯を食べ始めましたが。
順調そう・平気そうに見えても、内心では頑張っているんだなというのが改めてわかりました。
五月病を予防するためにはどうしたら?
五月病は、4月から新しい環境になれようとがんばり、連休明け、その緊張の糸が切れたときに起こる心や体の不調のこと
五月病による不調は「朝起きられない」「授業が身に入らない」「嫌な夢を見る」「夜中に目が覚める」「ごはんが食べられない」といった変化。
低学年は、「頭やおなかが痛く」なったり、「熱が出たり」することもあるんだそう。
五月病を予防するにはどうしたらいいか?記事に書かれていたことをメモします。
話をよく聞く・話す

パパやママといった保護者などが良く話を聞くことです。
ちゃんと顔を合わせて表情を見てお話してください。
笑い方や喋り方に何か変化があったら、不調の兆候かもしれません。
なんでも相談できる環境をつくっておくのがいいですね。
生活リズムを変えない
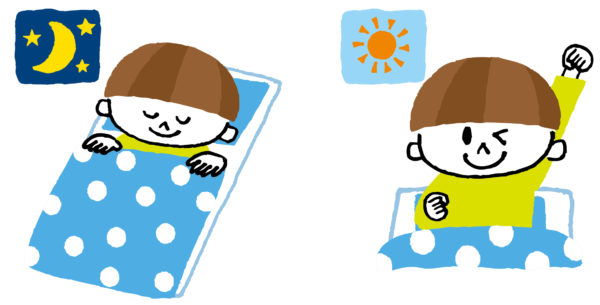
連休になると、つい夜更かししたりそのせいで朝起きるのが遅くなったり…生活リズムが崩れがちです。
連休明けにギャップを感じないように、連休中も朝起きる時間、夜寝る時間は4月と同じ時間にするようにしましょう。
日光を浴びる

太陽の光を浴びると、体内に「セロトニン」という体を活発にしてくれる物質が出るんだそう。
家でテレビやゲームばかりでなく、親子で公園に行ったり、散歩するのがいいですね。
カルシウム・タンパク質を摂る

カルシウム・タンパク質を摂ることも、五月病を防ぐのに良いのだそう。
牛乳や小魚、豆腐や鶏のささ身などで栄養面でもバランスを崩さないようにしましょう。
それでも落ち込んでしまったら、こどもにかける言葉は「がんばれ」?「のんびりやろう」?
「五月病」は年々低年齢化しており、まさに「現代病」ともいわれるんだそう。
東京都の南青山メンタルクリニック院長・武田浩一さんのお話では、
こどもが辛そうにしているときにかけたらいい言葉は、
「がんばれ」
ではなく
「のんびりやろう」
「何があってもわたしが守るから、のんびりやろう」
という声をかけてあげるのが良いといいます。
おわりに

連休明けになんだか疲れている、表情が暗いというのを見逃さず、つらそうなときは、「がんばれ」でなく「のんびりで大丈夫」という安心感を与える言葉がいいということでした。
「がんばれ」よりも「のんびり」という言葉がけのほうが、こどもは焦りも感じず安心しますよね。
学校生活にせっかく慣れたところに、楽しい楽しい連休。
連休が終わると「五月病」のような症状になるというのは、私自身も何度も経験済みなのでよーくわかります(^_^;)
その遺伝を受け継ぐわが子は、大丈夫だろうか?とつい心配になってしまいますが、親ができることは、プレッシャーを与えず、話をよく聞くこと。
こどもはまだ6年しか生きていない小さな体で、毎日いろいろなことを考え、学んでいます。
子どものペースでゆっくり乗り越えていけたらいいなと思います。
【こちらの記事もどうぞ】





